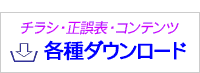書評・紹介欄
本ページ内の文書は原書紙誌様より許可を得て掲載しております。 書評の著作権は評者あるいは原書掲載紙誌に属します。書評記事の無断転載を禁じます。
飛田多喜雄先生に学ぶ
(東京法令出版「月刊国語教育」2011年2月号)
本書は、国語教育実践理論の会(略称KZR)会長であった故飛田多喜雄氏の業績とその遺徳を偲んで、氏の薫陶を受けた会員の論考を中心に編纂刊行されている。
「はじめに」の中で現会長の澤本和子氏が飛田多喜雄氏によるこの研究会の研究姿勢を紹介している。「人数は少なく、結びは堅く、研究は本格というのが、K・Z・Rの本領である。他の祖述や時流の迎合ではなく、不変の一道に情熱を傾けるのが私共の信条であった」とある。
本書には、冒頭に特別寄稿として、野地潤家氏による「国語教育史上の位置と業績」と題した論考が収められている。この中で野地氏は、飛田多喜雄氏の業績に関して「戦後の国語科教育課程の創成、整備、改善・改訂の事にも、協力者として終始深くかかわられ、国語教育の実践・研究のための情報・資料の確保と提供、また国語科教科書の編修・著作にも長い年月携わられ、大きい寄与をされた」と称えられ、その足跡を「昭和期国語教育界にあって、前後63年間もたゆみなくつづけられた活動とそこに営々と築かれた業績は、にわかには類例を見いだしがたい、独自のめざましさを持っている」と位置づけている。
本書の第1部には「理論」「実践」に関する27名の会員の論考が、また「地区活動」に関して7つの研究会からの論考が寄せられている。第2部は「資料編」として、飛田氏の「略歴と著作目録」、飛田氏との思い出が三氏によって綴られている。
本書を、今後の飛田多喜雄研究と国語教育の研究と実践に向けた良きガイドブックとして、座右に置かれることをお勧めしたい。
<評者>大内善一
比べ読みの可能性とその方法
(東京法令出版「月刊国語教育」2011年1月号)
まだ20代の教師4年目に南の島の学校で初めて試みてから続けられた「比べ読み」を、船津啓治氏は長い年月をかけて育てあげた。大げさかもしれないが、それは人生につながりや絆を築くための技法だと言ってよい。「比べ」ることで、私たちは複数の対象の間に共通点を見つけ、すぐその後に相違点を見つける(あるいはその逆)。そうすることで、「比べ」るまで気づかなかったことが見えてくる。「比べ読み」がそのような発見のための「窓」となると本書は教える。それだけではない。著者の「比べ読み」が育てるのは、個人内の既知と未知とを、そのひとの現在と過去と未来とを、忘れていた記憶と今とを「つなぐ」力だ。その「つなぐ」力がひとの成長と発達を促すことを、本書は曇りのない丁寧な筆致で明るみに出した。
たとえば本書第3章第4項「単元 絵本とテレビ絵本を読み比べて」に示された「発問」群は児童の思考を動かし、発言を促すプロンプツ(起点)となる。そこには、テクストと自身の既知・既有の知識・経験との間につながりを見つけながら、児童たちが頭と心を動かすような工夫が施されている。このような企てが児童の読む力の成長・発達を絶え間なく励ます。井上一郎氏や村井万里子氏の研究に多くの示唆を受けながら、それらを本書で柔軟に生かすことができたのも、南の島での著者の経験とそこに生まれたつながりと絆のゆえであろう。著者の「比べ読み」は諸事象を二重の景として読むための「窓」であり、私たちの一回限りの出会いをゆるぎない絆とする「窓」でもある。
<評者>山元隆春
入門期のコミュニケーションの形成過程と言語発達
幼児教育と学校教育との円滑な接続は、現代の重要な教育課題の一つである。しかし、そこで必要な指導の原理は、必ずしも共有されているわけではない。このような現状において、本書は、入門期(小学1年生)の子どもたちの言語発達とそれを支援する指導原理を、社会文化的アプローチから実証的に示した画期的な書である。
本書の構成は、「入門期の学習指導に関する先行実践の検討」、「入門期の学習指導に関する臨床研究」、「論理的思考力の発達」、「書くことの指導原理」という4部構成になっている。生活綴り方教師による入門期指導や、著者が参与観察を続けてきた橋本須美子教諭の実践をはじめ濱本滝一郎教諭や著者自身の実践成果の検証を通して、入門期の指導原理が構築されている。個々の学習者から「存在証明としての言葉」(キャズデン)を引き出す指導や理論的思考力を育てる説明的文章の指導、書くことの指導等の検証を通して、「一次的なことば」から「二次的ことば」への入門期指導で必要な手立てが明らかにされている。
それらは、談話分析等に基づきながら的確に、しかも読者の興味が高まるように記述されているので、子どもたちの学習の様子にひきこまれてしまう。また、先行実践の考察から一貫している入門期における学習環境デザインの重要性の指摘にも説得力がある。さらに、「じどう車くらべ」や「どうぶつの赤ちゃん」等の実践には、教材研究と指導の豊かなアイデアが満ちている。まさに、本書は、入門期の多様な子どもたちの指導をめぐる必読の書である。
広島のものづくり先進企業
(福山商工会議所所報 「商工ふくやま」2009年6月号、「備後の本棚」)
本書は、広島経済大学「広島地域ものづくり事情」の講義録、2007年度分を1冊の本として編集されたものです。 講義を担当したのは、さまざまな創意、工夫と努力で独自の製品を開発し、新しいビジネスモデルを立ち上げている先進企業です。日本ばかりでなく世界の市場で大きな成果をあげる過程での、各社に共通した創意工夫・チャレンジ精神など、困難に立ち向かう企業努力は人々に感銘を与えます。学生をはじめ、若手社会人、企業を目指している人などにも貴重な参考情報として活用できる内容となっています。
漱石作品を読む ―「二七会」輪読五十年―
国語教師にとって見逃せないの本が出た。漱石の作品を読み続けてきた研究グループ二七会の記録である。
二七会は1952(昭和27)年に広島大学教育学部高校国語教員養成課程入学の学生が56(昭和31)年に始めた輪読会である。卒業後も今も続く会の足跡を記したこの本は、輪読会の様子(第一部)、教材化と実践報告(第二部)、作品研究(第三部)、研究旅行などの活動報告(第四部)からなり、具体的な会の活動の有様が分かる。
教える営為は自らも学ぶことで可能となるが、教師の意識も変ってきて、建前だけになりかねない危うさがある。教材研究は指導書に委ね、学習者との検討よりAV利用の絵解きを選び、授業成果の判定となるテストまでが既製のを利用する傾向がある。時代相もあるとは言え、教員のその姿勢が教室から活力を奪ってはいないか。
この本にはそれと対蹠的な自己研鑽に努める教師の姿がある。原爆の焼跡の残る時代に発足した会は、半世紀を超え600回続いてきた。この愚直なまでの研究心の持続は、会員の誠実さと研究の核の存在(野地潤家氏)で実現した。これを教育に希望を託せた時代の記念碑にしてはなるまい。今こそ必要なものである。評者の乏しい体験でも、同僚と始めた輪読会があって、辛うじて教師を続けられた。
会員諸氏に敬意を払うと共に、現在教職にある人々に、この先達たちの稀有な記録を一読するようお勧めする。
<評者>桑名靖治
アメリカ連邦政府の思想的基礎 ―ジョン・アダムズの中央政府論―
(月刊「MOKU」2008年10月号 MOKU出版株式会社)
隠れた名君、ジョン・アダムズ
日本国民は政策や政治家に対し、往々にして冷ややかである。だが海の向こうのアメリカでは、候補者を支援する人々が、興奮し希望に満ちた顔をしている。どうしてこうも反応が違うのであろう。
本書は、合衆国第二代大統領ジョン・アダムズの分析を通して、米政府の底にある思想を明らかにする。
アダムズは、ワシントンのようなカリスマ性によってではなく、行政制度によって政治体を確立させた人物だ。これまでの研究において無能と軽視されてきたアダムズ。だが、筆者は建国の熱に浮かされることなく冷静に国を見つめるアダムズの姿を見せる。
国の根底を知ることで、アメリカという国を新しい視点で見ることができるかもしれない。
野口雨情そして啄木
童謡詩人の雨情が啄木と札幌で出会ったのは1907年(明治40年)、小樽日報の創刊に加わった時。2人は「わがまま」な性格など生い立ちや北海道への漂白の境遇での共通点があって急接近、濃密な交際になります。が、主筆排斥の企てのなか、啄木が不信感を募らせたのはなぜか。啄木の当時の回想文を比較・検討し、くい違いを指摘。啄木の記述に真実性を見出します。
伝え合いを重視した高等学校国語科カリキュラムの実践的研究
新しい学習指導要領に「伝え合う力」の育成は継承された。また、他教科・領域を視野に入れた系統的な指導が、これまで以上に求められるであろう。本書は、最新の教育理論や認知心理学などに学びつつ、「伝え合い」を重視した高等学校国語科カリキュラムのあり方を、10年間にわたって模索し、その過程と結果をまとめたものである。
著者は「伝え合いを重視した国語科学習指導」を「テクスト、人、自己」の三者間の「伝え合い」(相互関連)を生かした授業であると定義する。そして、これらの伝え合いを豊なものにして、言葉の力を育むことのできる国語科カリキュラムをどのように構想するかについて考察している。具体的には、「制度化されたカリキュラム」と「計画されたカリキュラム(年間指導計画)」をどのように関連させるか、「教材内容」「教科内容」「教育内容」を系統的に配した「計画されたカリキュラム」をどのように構想するのか、その「計画されたカリキュラム」をどのように「実践されたカリキュラム」へと移していくのか、さらに「実践されたカリキュラム」を通して学習者はどのように学び、成長していくのか(経験されたカリキュラムの内実)を、「総合的な学習の時間」や学習者の生活背景まで視野に入れて追究している。このカリキュラム開発研究は、OECDの内部機関であるCERI(教育研究革新センター)の提起した「学校に基礎を置くカリキュラム開発」の実践ともみることができる。このような方法に基づくカリキュラム開発研究は、少なくとも高等学校の国語科カリキュラム研究では初めてである。
高等学校に焦点をあてて書かれているが、小中学校の先生にも学ぶ点が多くあるはずである。是非、手にとっていただきたい。
<評者>大槻和夫(安田女子大学教授)
大正期における読み方教授論の研究―友納友次郎の場合を中心に―
我々国語教育史を学ぶ者にとって友納友次郎は、とても気になる存在である。
現代に通じる先進的な論を主張しているものの。芦田恵之助という太陽のような存在の陰となり、十分に研究されてきたとは言えないのである。
特にこれまで友納友次郎は、綴り方教育論を中心に研究されてきた。友納の読み方教育論については、小田迪夫氏の一連の論考(「大正初期の非文字文学教材の読みの理論」昭和51、等)があるものの、特に文学教材の読みについては、ほとんど先行研究がないのが現状だろう。
その意味で、この書のもつ意義は大きい。
本書は、著者の修士論文を軸にした第1部「大正期における読み方教授論の研究」と、それ以降に書かれた論攷と口頭発表3編とを収めた第2部、年譜・年表の第3部とからなる。
中でも本書の中心は、第1部の「第二章 友納友次郎の読み方教授法の成立」と「第三章 友納友次郎の読み方教授論の展開」にある。それぞれ、友納の大正期の著作である『読方教授法要義』(大正4)と『読方教授の主張と実際』(大正9)が詳細に分析されている。
友納のこれらの著書が執筆された時期は、明治期の教式中心の教授法が批判され、国語教材研究における形式と内容の統一が求められた時期である。
しかも、形象理論が成立する(垣内松三『国語の力』大正11)以前であり、文学教材が主流となる第三期国定読本の前である。
すなわち、これらの友納の著作を分析することによって、形象理論以前の文学教材の読みはどのように考えられていたのか、また、非文字教材の読みはどのように捉えられていたのか、という問題に答えることになるのである。
筆者は、その友納の読み方教授論の核心を、「文旨論」と「教授規範」に見出している。
その意味で、読者は、第?部に収められている紀要論文と口頭発表稿を、まず、はじめに読んだ方がよいかもしれない。そこには筆者の友納論の精枠が述べられているからである。
私は、特に、友納の「文旨論」を読み、その先駆性に心を惹かれた。
友納は「文旨」を、「顕在的文旨」と、「潜在的文旨」に二分し、それぞれ「形態」(形式)と「文旨」との関係によって、さらに細分している。
このような文旨の表れ方によって教材の読みを規定しようとする試みは、筆者が指摘しているとおり、まさに「先導的な試行」である。
益地憲一氏のこの労作によって、友納友次郎の読み方教育論の史的意義が再評価されたと言えるだろう。読解力に注目が集まっている今、広く読まれることを望みたい。
<評者>山本茂喜(香川大学教育学部)
キャリア教育推進のための研修マネジメント―福山市立網引小学校における実践研究の展開―
「キャリア教育」の概念は新しいものではないが、社会や子どもの変化に応じて、改めて「キャリア教育」の視点に立った新しい教育実践が求められている。
本書は、生活科や総合における「地域学習」を中心に各教科・領域での「かかわり合い」を深める学習を基盤として、キャリア教育の推進に取り組む福山市立網引小学校の実践を通して、学校における校内研修のマネジメントサイクルをどのように構築し、機能させていくかを提案する。
学校教育の諸側面からキャリア教育推進上の課題、校内研修マネジメントの構築・機能化、授業研究の具体例、キャリア教育の視点に立った児童活動・生活指導について、詳細に考察する。
アメリカ合衆国におけるインクルージョンの支援システムと教育的対応
特殊教育の改革を模索し変容を探る具体的な動きは、教育におけるインテグレーションの取組みに見られ、1990年代の欧米諸国のインテグレーションに対する動向は、3つに区分されるとしている。
1 イタリアなど特別な学校なき障害児教育を推進するタイプ、2 アメリカなど通常の学校におけるインクルーシブ教育を原則とするタイプ、3 ドイツなど特別な学校の教育機能を活用しつつ、通常学校における障害児教育を推進するタイプ。インテグレーション教育に本格的に取り組み、今ではインクルーシブ教育の段昭を標榜するアメリカは連邦国家であり、教育の主権は各州に委ねられている。難しい課題に挑戦し、その実態と問題点を究明しようと取組んだもの。
同書の特色は、歴史的経緯とその背景を究明して、インクルーシブ教育の基盤を明らかにするととともに、「ピア・チュータリング」や「協同学習」に焦点をあてている。
言葉を考える ――中学生の日本語探索――
老婆は一日にしてならず。
「国語力」や「言語事項」が重視されてきたから何か指導を強化しましょう。あ、この本の副題「中学生の日本語探索」とある。参考になるかしら。と思って手にとっても無駄ですよ。ここにある実践は並々ならぬ日本語力がなければ真似することはできません。人一倍日本語に敏感でなければできません。そうである自信があれば、ご覧ください。 恒心なければ恒産なし。 国語力なんてものは、年に一つ単元を設定したくらいでどうにかなるものではありません。毎日毎日、積み重ね、折に触れて言葉の刺激を与えなければ、生き生きと働く国語力は生まれません。いつも変わらぬ心配りが必要です。そこではじめて着実な成果が上げられるのです。
そんな持続力に自信があれば、この実践、やってみる価値があります。
鉄は熱いうちに打ち続けよ。
生徒は一人一人違います。持っている語彙も感覚も興味も問題解決能力も。そんなばらばらな生徒たちすべてを熱くする方法が、数々紹介されています。しかし問題はその後。生徒一人一人の熱くなりようを見極め、それに応じた方法・タイミングで打ち続けなければ、鍛えることはできません。その優れた実践例が満載です。応用できますか。自信があれば、どうぞご参考になさってください。
最後に、自信など無いが、目標は高く持ちたいという方、是非この本をご一読ください。国語教室のあるべき姿が、ここにはあります。
<評者>愛甲修子(東京学芸大学附属高等学校大泉校舎)
戦後における中学校古典学習指導の考究
高校卒業後も(折にふれて読む、とまでいかなくとも、せめて)古典を手に取ったことがある、という人は一体どれぐらいいるのだろうか。
おそらく多くの人にとって古典とは、授業や受験でのみ関りを持ち、卒業と同時に縁遠い存在となる一教科でしかない。古典を教える者として一抹の寂しさも覚えるが、現実はそんなとことであろう。しかし、だからこそ我々は、人々が古典と触れ合うほぼ唯一の場である中高等学校の授業を意味あるものとしなければならない。
その際、我々にとって力強いてびきとなるのが、全国各地で行われてきた実践の記録である。そこには古典教材をめぐる教師と学習者との格闘の跡が刻み込まれており、我々はそうした実践記録と向き合うことで、古典教育の新たな課題や可能性を発見しうるだろう。渡辺氏が本書をもって成し遂げているのは以上のような実践記録の一つひとつの真摯な対話であり、そこから戦後古典学習指導の成果と課題が引き出されているのである。
さらに渡辺氏は数多くの実践記録のなかから「ある時期の古典学習指導の特徴をあらわあす実践」や「時代の古典学習指導を切り拓く契機となった実践」など見て取り、それらをもとに戦後古典学習指導の展開を跡付ける。これは日頃から多くの実践記録と向き合ってきた渡辺氏ならではの仕事といえよう。
古典の授業を学習者にとって意味あるものとしたい、そうした思いを持ったとき、先人の実践記録との対話を重ねた本書はよいてびきとなるであろう。
<評者>武久康高
国語科教師の専門的力量の形成―授業の質を高めるために―
教員の不祥事、指導力不足、不適格教員の報道など、教師に対する世間の風当たりは厳しい。いっぽうで、世界一忙しいとも言われる日本の教師の仕事量。心が傷ついて休職を余儀なくされる教師が、毎年増え続け、4000人を超えるという事態。こんな厳しい状況下、多くの教師は、子どものために良質の教育をしたいと願っている。本書は、国語科の専門的力量形成に絞って、教師のこの願いに応えようとしたものであり、当該領域での必読文献である。
専門的力量形成は、大学における養成教育、卒業後の現職教育と生涯続く道である。本書では、大学での養成教育として、教科教育法の授業、卒業論文指導を生涯学び続ける基盤作りとなるよう工夫している。例えば、文学教育を巡り著者と須貝千里氏が議論する方法によって、研究的立ち会い講義は、どんな本を読むより、各々の主張がよく分かる。
また、大学卒業後の現職教育で、どのような力量形成を図るべきかを、校内研などのフォーマルな研修、自主サークルなどの自己研修のあり方で示している。さらに、授業力の高め方、国語科授業研究の新しい方法などを紹介しながら、具体化している。著者らしく、広い視野からまとめつつ、同時に具体的に論じているので、山頂から全体を俯瞰した後に望遠鏡で細かく見ていくような感覚である。
読了していちばん心に重く響くのは、子どもたちのために「授業者として成長したい」という「強烈なねがい」(7頁)を持っているか、という言葉である。私は、あなたは、どうですか?
<評者>松崎正治(同志社女子大学現代社会学部教授)
本書は1980年代以降の内外の教師教育研究成果を踏まえ、「国語科教師」の専門的力量形成を、言語技術教育研究に軸足を置いてまとめた労作である。1992年以降のものに新たな論考も加えた大著で。この分野での一つの立場を語る上での到達点を示すものと考える。
序文では、教師の資質・能力の向上を「授業力」として訓練し、評価しようとする昨今の動向に対し、「それだけでは、下手をすると授業の表面的な部分だけを見たり真似したりすることになりかねない。」と、複数の尺度からの教師の指導能力評価の重要性を提起する。それは「現象としての授業」を見るのではなく「そこに潜んでいる内面的なもの」すなわち「哲学としての授業」を見ることだとする。後者は教師自身の学習履歴、つまり成長過程の明示化を重視する立場であり、それは学習者としての子どもの学びの履歴を重視する立場でもある。こうした著者のスタンスに共感する読者は多いであろう。
(中略)
筆者の研究関心から見ると、第1部、第2部が圧倒的に面白い。斉藤喜博の「介入授業」について、先行研究を踏まえながら持論を展開する第6章は圧巻である。研究としての質の高さと、筆者の研究と実践への情熱が随所ににじみ出ている。
第3部は須貝千里山梨大学教授との「立会い講義」の実践報告を含む、開発的FD研究が興味深い。文学教育の根本問題を見直す教材を提供する内容、大学教員でなくとも、わくわくしながら読めるだろう。著者の「解釈」と「分析」を生かした授業デザイン論の問題としてみれば、須貝氏の批判等から両者を実践場面でどう組織するかが根本問題であることが再認識できて興味深かった。
最後に一言不満を述べるとすれば、「教師成長研究」と「国語科教師成長研究」の異同に関して、自明的に論が進められている点である。近接分野の研究者の立場から見れば、その定義を明示した上での論の展開を期待するのである。
本書との出会いに感謝したい。
<評者>澤本和子(日本女子大学教授)
朝鮮戦争と中国―建国初期中国の軍事戦略と安全保障問題の研究―
中国の安全保障から分析した朝鮮戦争
第二次世界大戦後まもなく勃発した朝鮮戦争は、これまで世界的な米ソ冷戦体制の東アジアにおける形成の発端となる大事件として語られ、日本ではソ連、北朝鮮、米国、韓国が、何故、どのような意図で開始したのかをめぐり、また、その直後に締結される日米安全保障条約、サンフランシスコ講和条約、日華平和条約と密接に連関して論争・研究されてきた。(中略)
これまで朝鮮戦争は米ソ「冷戦」体制の朝鮮戦争という観点から論じたものが多いが、本書は当時の中共指導部がソ連をはじめとする社会主義陣営の一員として、建国したばかりの自国の当面している「安全保障問題」をいかに認識し、朝鮮戦争を戦ったかを論じていることに特色がある。注目すべき第一は、1949年末までに、中国大陸全土をほぼ制圧した毛沢東をはじめとする中国指導部の建国直後の優先課題が台湾「解放」問題であったことである。本書が注目するもう一つの中国の安全保障上の重大問題は、いうまでもなく中国志願軍が参加した朝鮮戦争の軍事上の推移である。第三は、中国南部の当時、なお、国府軍が駐屯していた中国・ベトナム国境地帯の安全保障とそれと密接に関連するホー・チ・ミンに率いられたベトナム独立運動に対する支援である。(中略)
本研究書が関心を寄せて、追求しているもう一つの問題は、朝鮮戦争を通じて米国・韓国・朝鮮を中核とする国連軍と戦った中国・北朝鮮及びソ連はさらにはベトナム民主主義共和国間の当時は「一枚岩」とみられた「社会主義陣営諸国」の間の国際関係の問題である。朝鮮戦争期間中、中国の国防予算は50パーセントをはるかに超え、しかも、ソ連の中国に対する兵器支援は無償ではなく、利子さえ付いていたため、建国直後の中国の経済、文化建設は困難を極めたことである。これらの事実は後の中ソ対立の原因になった。中国・ベトナム関係では、ベトナムの対米、対仏独立戦争にたいする中国の支援について中越両指導部の間で方針の食い違いがあったことが本書で指摘されている。朝鮮戦争終結直後の1954年のジュネーブ会議で中国の周恩来首相の主張により、北緯17度線の境界線で休戦協定が成立したことにベトナムが強い不満を持ったこともその一つである。
朝鮮戦争という国際紛争を通じて、台湾「開放」をめぐる国際環境は大きく変動した。日本は米国と講和条約と安保条約、さらには台湾の中華民国との間に平和条約を締結し、米国の第七艦隊は中国の台湾「解放」を不可能とする状況を作り出した。中国指導者は、朝鮮戦争を通じて、アメリカ、ソ連との関係のみならず、ベトナムや中立主義を表明していたインド、ビルマ、インドネシアなどの諸国との関係についても、その認識を改めていった。これによって朝鮮戦争以後、中国が建国初期に唱えた植民地諸国の「武装による民族解放」モデルから、次第に平和共存路線へと対外路線を転換させることになったと述べる。
以上述べたように、本書はこれまでの朝鮮戦争と中国に関する研究および資料状況を実に丹念によんで、中国の安全保障という新たな視点から、中国にとっての朝鮮戦争を分析している点で説得力があるといえる。同時に、朝鮮戦争はソ連を中核とする社会主義陣営と米国を中心とする資本主義陣営との体制間の戦争、民族独立運動という側面を持つ世界的な戦争という視角からのアプローチも必要であるといえよう。
<評者>安藤正士(筑波大学名誉教授)
中国人留学生・研修生の異文化適応
中国人留学生の留学前の対日イメージに関して8名中6名が「先進国」という言葉を用いた。ただ、具体的な内容を見ると、「裕福」「お金持ち」といった抽象的、表面的なものに過ぎなかった。「現代の日本については、留学する前にほとんど知らなかった。具体的なイメージがなかった。」というのが本音のようだった。
しかし、実際日本に留学することにより、このような抽象的なイメージがより具体的に、客観的になった。「物価が高く、住みにくい」という印象も強かったが、一方で、「環境がきれい、サービスが良い」というイメージもあった。
また、留学前後のイメージの変化について、「日本に来る前に、日本人はお金持ちで裕福な生活を送っていると思っていたが、住んでみると家が狭いし物価も高く、食事にしても買い物にしても、常に値段を考えながらやらなければならない。むしろ中国にいた方が豊かな生活が送れるのではないかと思う」といったように、日本はイメージしていたほど豊かではないことを多くの中国人留学生が指摘した。(中略)留学生が来日前に持っていた対日イメージは、一般論の域を出ておらず、古い情報が多かったが、来日後、現代日本の社会状況に戸惑いや驚きを感じているようであった。さらに(中略)日本社会が外国人に対してまだ開かれておらず、特にアジア系の外国人に対して偏見を持ていることが共通して語られた。(本文より)
コンピュータが支援する日本語の学習と教育―日本語CALL教材・システムの開発と利用―
日本語教育における最新のCALL研究の全体像が具体的にわかる
現代情報社会における日本語教育の背景から、日本語CALLの開発・利用に関する実践的な事例までを、多面的・具体的に検討し、全体像と方向性を探るもので、電子メディアやコンピュータ利用の調査・分類化の作業を通しての日本語CALLの開発や利用の位置付け(1,2章)、コンピュータによる「文字の扱い」を中心に基本的な課題解決を検討(3~6章)、音声・映像を利用した学習を教育的な視点から考察(7,8章)、マルチメディアとしての日本語教育CALLシステムの実践的な可能性(9章)、高度なマルチメディア利用の具体事例提示とパッケージ型とネットワーク型のシステムについて教師支援を含めた日本語CALLの方向性を包括的に提案する(10~15章)。
書評の著作権は評者あるいは原書掲載紙誌に属します。書評記事の無断転載を禁じます。